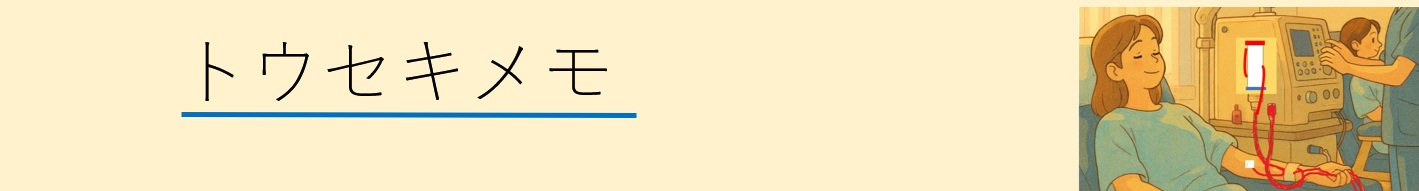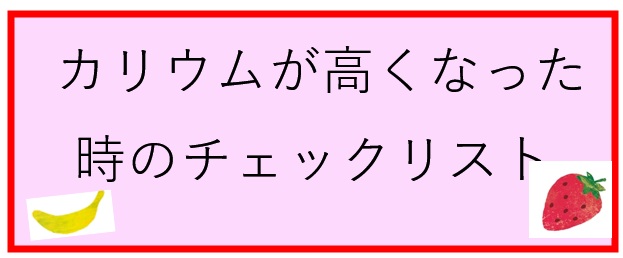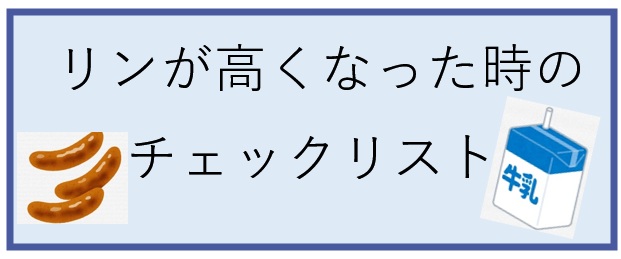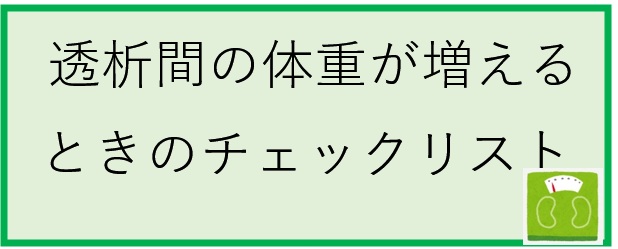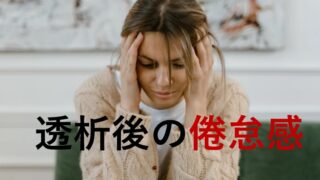【透析ニュース:透析患者への偏見】透析は延命治療?緩和ケアへの取り組み

透析患者に対し、どのような偏見があるのかというと、
偏見と批判
・透析になったのは、生活の乱れと自己管理が悪いから自己責任
・健康でいる努力を怠った人に税金(透析費用)を月40万円かけている
でも、透析の原因になった病気も人それぞれ違うし、一概には言えません。
少なくとも透析患者になりたくて、なった人は一人もいないと思います。
透析患者への無理解は、職場での理解が得られないことや
家族でも透析のことを理解してくれないこともあるし
実際のところ、透析を経験している本人にしか分からないこともあります。
「命をつなぐ行為」 “透析大国”日本、一方で進まない患者への理解 「“輸血に使われたくないから献血しない”という誤った知識も…」
ABEMA Prime 2025/02/09
■透析患者への偏見
透析を必要とする人は日本国内に35万人ほど、患者数の人口比で世界3位の“透析大国”だ。しかし、理解不足から患者への偏見も多く、“透析=生活習慣病や糖尿病”というイメージも見られる。『ABEMA Prime』では当事者とともに、どうすれば患者への理解が広がるのかを考えた。●透析患者に向けては「自業自得」といった声も向けられる。しかし、透析をしている弁護士のMiiさん(女性、30代)は「『透析に至るような人は自堕落な生活をしていた』というスティグマ(偏見・差別)が大きいのが、一番問題だ」と語る。
●日本腎臓学会の前理事長であり、川崎医科大学 高齢者医療センター 病院長の柏原直樹氏は、偏見の要因として「知識不足と寛容のなさ」を挙げる。「腎臓病になれば、食事療法と生活管理が必要になる。うまくいかなければ腎機能の低下が加速することは事実だが、それが主な原因にはならない。糖尿病の場合も、同じような食生活や運動不足をしている人が、同じように発症するわけではない。遺伝的な要因などもあり、自分でコントロールできないもの。偏見の対象になってはいけない」。
中には「健康リテラシーがない患者」がいるものの、「できない理由がある人もいる」という。「自堕落と思われるような生活にも、何かしらの要因がある。そこを見ずに、勝者の論理で『自己責任だ』と決めつけるのは良くない」と語る。
■透析は「延命治療」か?
透析患者の緩和ケアとして、CKM(保存的腎臓療法)に注目が集まっている。日本腎臓学会などの情報によると、末期腎不全の患者が透析や移植を選択しない、透析を中止したい場合に、身体的・心理的苦痛の軽減のために実施される保存的な治療を指す。
Miiさんは「“延命治療”だと思っている」立場だ。「透析しなければ2週間程度で終わる命を、数珠つなぎのように延ばしてもらっている。若い世代で透析を始めれば、20〜30年と仕事を続けられる人もいる。社会保障として、とてもありがたく感じている」と感謝する。柏原氏は今の取り組みとして、「高齢化や合併症により、血液のシャント(動脈と静脈をつなぎ合わせた血管)が閉塞するなど、透析をやめなければいけない、もしくはやめたい人がいる。そうした人々への緩和医療として、CKMのマニュアルやガイドライン作りを行っている」とした。
≫ABEMA Prime
動画のなかで、私が気になった箇所は、緩和ケアについての言及部分です。
どうしても、透析を続けられない状況になったときのために、これから緩和医療のしくみを作っていくようです。
緩和ケアへの取り組み(透析をやめたいときは?)
<動画最後の29分部分>
柏原医師:今、様々な理由で透析を見合わせなければならないとか
あるいは透析を何十年もやってきたけど、そろそろやめなければいけないといいう事例がだんだん増えています。
高齢化、様々な合併症、例えばシャント閉塞してもシャントを作る場所がなくなってくるとか。
何十年も透析をやってきたがいろいろな事情で透析をやめなければならない、
本人も、もうやめたいとおっしゃるような方がいらっしゃいます。
そういう方はどうするのか?
柏原医師:透析をやめたらいろいろな症状がでてきます。
それに対する緩和医療が必要だということで、今、緩和医療のしくみを作ろうとしています。
CKM(保存的腎臓療法)の具体的なマニュアルやガイドラインを作ろうとしている所ですそれは、安楽死のようなことには、つながりませんか?
柏原医師:そこがものすごくセンシティブな部分ですよね
透析をやめるって言ってもいいんですか?
「私は透析を受けたくないです」と言っていいんですか?柏原医師:言っていいんです。本人が希望して家族も納得すれば
それは、死を覚悟しないと言えないことですよね?
柏原医師:言えない事ですね
それも理解されていて、ご家族もそれに同意している
もちろん医療者もそこに関与している
何度も話し合いを繰り返して同じ結論にいたったら、はやり透析をやめるということになります。
≫動画はこちら
※ CKM(保守的腎臓療法)の治療が受けられる病院は、今のところ限られているようです。全国どこでも等しく受けられるという体制はまだ整っていないようです。